原価高騰を乗り越えるために─
「当社の原価構造はどうなっているのか?」を専門家と解く
文責:株式会社 Revitalize 代表取締役兼 CEO 片桐豪志
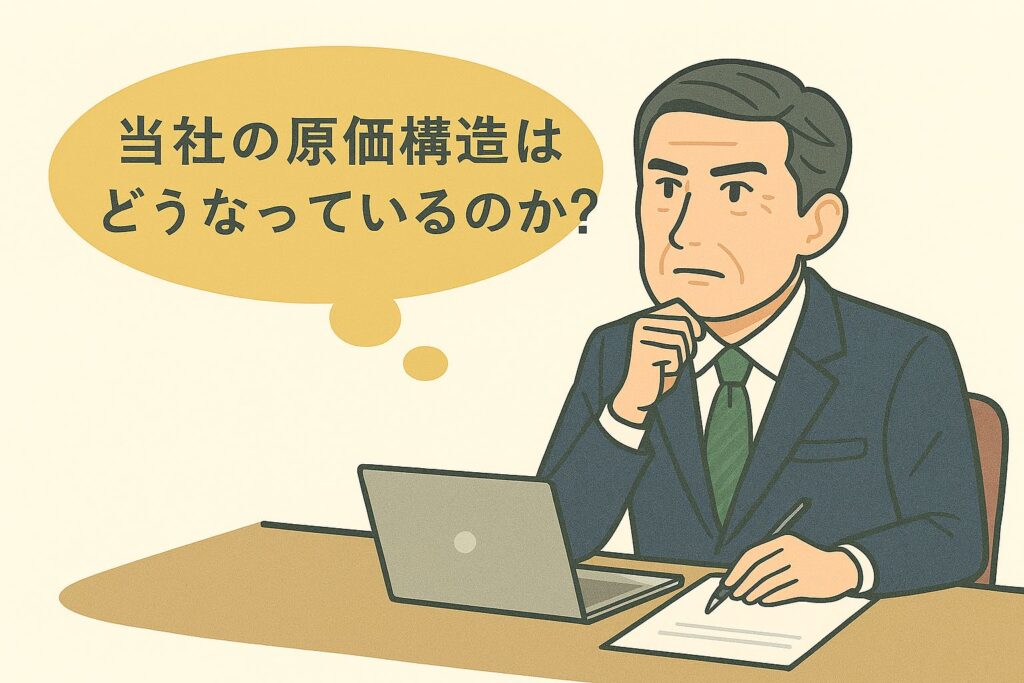
はじめにー本記事の目的と東京都支援の概要
原価高騰で利益が圧迫されてお悩みの中小企業経営者は多い。そこで、公的な支援を活用して、専門家と一緒に「原価構造とは」を明らかにし、実務に落とし込む方法を考えてみましょう。
東京都中小企業振興公社が実施する「スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業」では診断からツール導入支援、専門家の伴走までを利用可能で、原価構造や利益構造を把握し、短期・中長期的な施策を相談することができます。
原価構造とは — 基本概念
原価構造とは、製品やサービスを提供するために発生するコストの構成を要素別に分解した全体像です。主要な構成要素は直接材料費、外注費、直接労務、製造間接費、販管費です。原価構造を正確に把握すると、粗利率低下の原因が材料価格なのか販管費なのかを明確に判断できます。
東京都の支援事業で相談できること
上述の東京都中小企業振興公社の支援事業では、おもに公認会計士や中小企業診断士が決算データ等の企業から提出された情報を基に原価構造分析を行い、現状と課題の整理、粗利率低下の原因と優先施策を提示します。支援メニューは事前ヒアリング、原価計算ツールの選定からトライアル導入支援、把握した原価を基にした今後の価格転嫁交渉に向けたコンサルティングがあります。 ツールの導入費は先出なしで上限100万円まで助成されるため、多くのケースで無償でカバーされます。コンサルティング費用もかからないため、企業側では担当者を指名するだけで原価構造の把握が可能です。
業種別の焦点ポイントと相談事例
製造業では材料費と外注費が大きく、設備の減価償却や工場間接費の配賦方法が利幅に直結します。例えば自動車業界の原価構造は部品点数の多さとサプライチェーンの複雑性が特徴で、部品表単位で原価構造図を作り供給リスクとコストを紐づける原価構造分析が必要です。 SaaS業界では物理的な材料費は小さいものの、ホスティング費用、SREやカスタマーサクセスの人件費、CACが主要項目となり、顧客1アカウント当たりの単位原価とLTV/CACの整合性を評価します。アパレル業界では材料・縫製外注・在庫リスクとチャネル別販管費が焦点で、シーズン性を反映した原価構造を考える必要があり、在庫引当と値下げリスクも重要です。飲食業界、例えばラーメン店では、原価構造はスープ・麺・具材別の食材原価と客単価・回転率の組合せが利益を決めるため、店舗別原価構造図でメニュー別の採算を可視化します。
ご相談の流れ
ご相談の標準的な流れは、(1)応募と審査、(2)事前ヒアリングで企業側と事務局側で認識のすり合わせを行い、(3)公認会計士によるヒアリングとデータ提出、(4)公認会計士による原価構造の分析結果の提示と議論、(5)原価計算ソフトの選定・トライアル導入、(6)中小企業診断士等コンサルタントとの価格転嫁戦略の相談という順序です。
お問い合わせ方法と利用のポイント
応募フォームからご応募いただき、企業側で経営者や経営企画部門担当者、財務担当者などの担当者を指名してください。数字の裏にある運用ルールや現場の工夫は改善案の成否を左右します。事前ヒアリングから公認会計士との議論を経ると、優先的に取り組むべき施策が見えてきて、自社に合った原価計算ソフトも当たりをつけることができます。まずは東京都中小企業振興公社の支援事業の応募フォームからお申込みいただき(こちら)、事前ヒアリングの設定をお待ちください。
まとめ|東京都支援を使って原価構造を丸ごと診断する
原価構造がどうなっているかをやみくもに考えるよりも、専門家に伴走支援を受けながら原価構造を効率的に把握し、取り組むべき費用削減や生産性改善の項目の優先順位を見つけることが確実で迅速な打ち手です。 本事業では東京都の中小企業であれば業界は小企業が対象ですので、製造業や自動車業、SaaS系企業、アパレル業や、飲食店チェーンに至るまで、業種に応じた診断が可能です。是非ともご利用ください。


